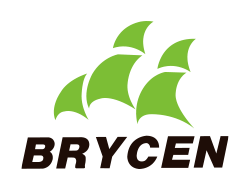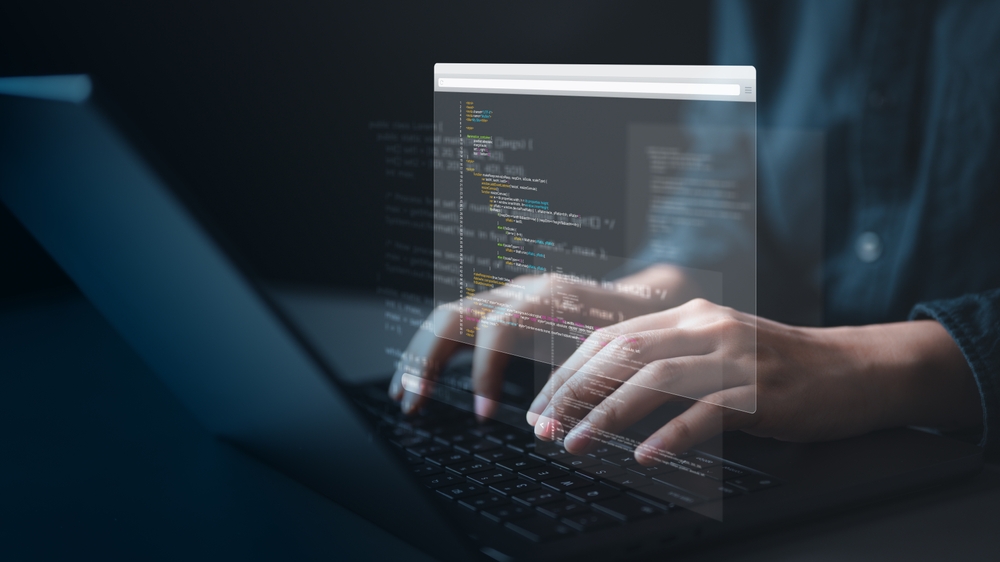システム開発プロジェクトの成否を左右する最も重要な工程が「要件定義」です。IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)の調査でも、システム開発の失敗原因の多くが要件定義の不備に起因するとされており、上流工程の品質がプロジェクト全体のQCD(品質・コスト・納期)を大きく左右します。
本記事では、要件定義の基本的な位置づけから、定義すべき項目、具体的な進め方、要件定義書に記載すべき内容、そして成功させるためのポイントまで体系的に解説します。 システム開発の発注や推進を担当する方は、ぜひ参考にしてください。
目次
閉じる
要件定義とは?システム開発における位置づけ
要件定義とは、システム開発の初期段階において、発注側の要望を踏まえて「何を開発するのか」「どのような機能や性能が必要か」を明確にし、関係者間で合意する工程です。ウォーターフォール型の開発プロセスでは最上流工程に位置し、ここで定めた内容がその後の基本設計、詳細設計、実装、テストのすべての工程の基盤となります。
要件定義と混同されやすい言葉に「要求定義」があります。要求定義は「発注側が何を実現したいか」という要望を整理する工程であり、要件定義は「その要望をどのようにシステムで実現するか」を技術的に定義する工程です。要求定義は要件定義の前段階、あるいは要件定義の最初のステップと位置づけられます。
要件定義があいまいなまま開発を進めると、想定と異なるシステムが完成したり、開発途中での仕様変更が頻発してスケジュールや予算が大幅に超過したりするリスクが高まります。発注側と開発側が綿密にコミュニケーションを取りながら、認識のずれをなくすことが要件定義の本質的な目的です。
要件定義で定義すべき項目
要件定義では、システムに求められる条件を多角的に整理する必要があります。定義すべき項目は大きく4つのカテゴリに分類でき、それぞれの抜け漏れがプロジェクト全体の品質に影響を与えます。ここでは、各カテゴリの内容と押さえるべきポイントを解説します。
- 機能要件
- 非機能要件
- 業務要件
- システム構成・技術要件
機能要件
機能要件とは、システムが「何をするか」を定義する項目であり、要件定義の中核を成す要素です。ユーザーがシステム上でおこなう操作と、それに対してシステムが返す処理結果を具体的に定義するもので、画面構成、データ処理、帳票出力、外部システム連携などが含まれます。
たとえば「受注情報を登録する」「在庫数量をリアルタイムで表示する」「月次レポートをPDFで出力する」といった内容が機能要件にあたります。機能要件の定義が不十分だと、開発側が意図を誤って解釈し、手戻りが発生する原因となります。
機能要件を洗い出す際は、ユーザーの業務フローに沿って必要な機能を網羅的にリストアップし、優先度をつけて整理することが重要です。
非機能要件
非機能要件とは、システムの「品質特性」や「運用条件」を定義する項目です。可用性(稼働率)、性能・応答速度、セキュリティ、拡張性、保守性、バックアップ・リカバリ方針などが含まれ、システムの安定稼働と長期的な運用を支える基盤となります。
非機能要件は機能要件に比べて見落とされやすい傾向がありますが、本番稼働後のトラブルに直結する重要な項目です。たとえば「同時アクセス数1,000ユーザーで応答時間3秒以内」「データのバックアップを毎日自動実行」といった形で、定量的に定義することが求められます。
IPAが公開している「非機能要求グレード」を参考にすると、非機能要件の項目を体系的に整理でき、抜け漏れの防止に役立ちます。
業務要件
業務要件とは、システム化の対象となる業務プロセスを定義する項目です。現行の業務フローを正確に把握したうえで、システム導入後にどのように業務が変わるのかを明確にし、「どの業務をシステム化するか」「どの部分は人手でおこなうか」の境界線を定めます。
業務要件の定義が不十分だと、開発したシステムが実際の業務にフィットせず、現場で使われないシステムが出来上がるリスクがあります。業務部門のキーパーソンからのヒアリングを通じて、暗黙知となっている業務ルールや例外処理も漏れなく把握することが不可欠です。
業務フロー図や業務ルール一覧を作成し、発注側と開発側の双方が同じ理解をもてる状態にすることが、業務要件定義のゴールとなります。
システム構成・技術要件
システム構成・技術要件とは、システムを実現するための技術的な基盤を定義する項目です。開発言語、フレームワーク、データベース、インフラ環境(オンプレミスまたはクラウド)、ネットワーク構成、外部システムとの連携方式などを明確にし、開発の技術的な方向性を確定させます。
技術要件の選定は、非機能要件で定めた性能やセキュリティの基準を満たすことが前提です。また、運用・保守のしやすさや将来の拡張性も考慮する必要があります。
既存システムとの連携が必要な場合は、インターフェース仕様やデータフォーマットの整合性も技術要件として定義する必要があるため、現行システムの技術的な調査も並行しておこなうことが重要です。
要件定義の進め方
要件定義は、発注側の要望をヒアリングするところから始まり、分析・整理を経て、最終的に要件定義書として文書化する一連のプロセスです。ここでは、5つのステップに分けて具体的な進め方を解説します。
- ステップ1:ステークホルダーの特定と現状の課題整理
- ステップ2:要求のヒアリングと要望の明確化
- ステップ3:要求の分析と優先順位付け
- ステップ4:要件への落とし込みと実現可能性の検証
- ステップ5:要件定義書の作成とレビュー・合意形成
ステップ1:ステークホルダーの特定と現状の課題整理
要件定義の最初のステップは、プロジェクトに関わるステークホルダー(利害関係者)を特定し、現状の業務課題を整理することです。経営層、業務部門の責任者、現場の実務担当者、情報システム部門など、それぞれの立場によって課題認識や期待する成果が異なるため、関係者を漏れなく洗い出すことがプロジェクトの出発点となります。
現行の業務フローやシステムの運用状況を調査し、「どの業務にどのような課題があるか」「なぜシステム化が必要なのか」を具体的に言語化します。現行システムが存在する場合は、その機能一覧や問題点の棚卸しも並行しておこなう必要があります。
この段階で課題の全体像を把握しておくことで、後続のヒアリングや要件整理の精度が大きく向上します。
ステップ2:要求のヒアリングと要望の明確化
ステークホルダーから具体的な要望をヒアリングし、「何を実現したいか」を明確にする工程です。ヒアリングでは5W1H(Why・What・Where・Who・When・How)を意識し、あいまいな表現を排除して具体的な要望として整理することが重要となります。
「Why(なぜ)」はとくに重要な観点です。ユーザーが口にする要望の裏側には、本質的な課題や目的が隠れていることが多く、表面的な要望だけを拾い上げると、課題解決につながらないシステムが出来上がるリスクがあります。
ヒアリングの際は、専門用語を避けてわかりやすい言葉で質問し、必要に応じて画面のサンプルや業務フロー図を提示することで、発注側と開発側の認識のずれを防止できます。
ステップ3:要求の分析と優先順位付け
収集した要求を分析・整理し、要求同士の関連性や矛盾点を洗い出したうえで、優先順位を付ける工程です。すべての要望を一度に実現することは予算やスケジュールの制約上困難であるため、「Must(必須)」「Should(重要)」「Could(あれば望ましい)」「Won’t(今回は対象外)」といった基準で分類し、開発スコープを確定させます。
要求の優先順位付けにおいては、ビジネスインパクトの大きさ、技術的な実現難易度、他の要求との依存関係を総合的に評価する必要があります。発注側の「すべて必須」という主張に対しては、開発側から実現可能性やコストへの影響を具体的に提示し、合理的な判断を導くことが重要です。
この段階での合意形成が不十分だと、開発途中での仕様追加や変更が頻発し、プロジェクト全体に悪影響を及ぼす原因となります。
ステップ4:要件への落とし込みと実現可能性の検証
優先順位付けされた要求を、具体的なシステム要件として定義する工程です。「何を実現したいか」という要求を、「どのような機能・性能・構成で実現するか」という技術的な仕様に変換し、実現可能性(フィージビリティ)を検証します。
実現可能性の検証では、技術的に実装可能かどうかだけでなく、予算・スケジュール・リソースの制約の中で実現できるかを総合的に判断します。実現が困難な要件については、代替案を提示して発注側と協議する姿勢が重要です。
この段階では、プロトタイプや画面モックアップを作成し、発注側に完成イメージを視覚的に確認してもらうことで、認識のずれを早期に発見・修正できます。
ステップ5:要件定義書の作成とレビュー・合意形成
定義した要件を要件定義書として文書化し、関係者のレビューを経て正式に合意を得る最終ステップです。要件定義書は、発注側・開発側の双方がプロジェクト全体の方向性を共有するための基盤となる文書であり、「誰が読んでも同じ理解ができる」明確な記述が求められます。
文章だけでは伝わりにくい部分には、業務フロー図、画面遷移図、データモデル図(ER図)などの図表を活用して視覚的に補完することが効果的です。また、「現行仕様通り」といったあいまいな表現は避け、具体的な仕様を漏れなく記載する必要があります。
レビューでは、発注側のキーパーソンに内容を確認してもらい、修正が必要な箇所があれば反映して再度レビューをおこないます。最終的に双方が合意した要件定義書が、後続の設計・開発工程の契約条件としての役割も果たします。
要件定義書に記載すべき主な項目
要件定義書の記載項目はプロジェクトの規模や特性によって異なりますが、共通して押さえるべき基本項目があります。ここでは、要件定義書に記載すべき4つの主要な項目カテゴリを解説します。
- プロジェクト概要・目的・スコープ
- 機能要件一覧と非機能要件一覧
- システム構成図・業務フロー図
- スケジュール・体制・前提条件と制約事項
プロジェクト概要・目的・スコープ
要件定義書の冒頭には、プロジェクトの背景、目的、開発スコープを明記します。「なぜこのシステムを開発するのか」「どの業務範囲を対象とするのか」「今回の開発に含まない範囲は何か」を明確にすることで、関係者全員がプロジェクトの方向性を共有できます。
スコープの定義はとくに重要です。開発範囲があいまいなまま進めると、「これも対応してほしい」というスコープクリープ(要件の肥大化)が発生し、コストや納期の超過を招きます。
対象外とする機能や業務についても「今回のスコープには含めない」と明記しておくことで、後からの認識のずれを防止できます。
機能要件一覧と非機能要件一覧
システムが備えるべき機能と、品質・運用面の条件をそれぞれ一覧化して記載します。
機能要件は画面単位や業務プロセス単位で整理し、各機能の入力・処理・出力を具体的に定義します。非機能要件は、可用性、性能、セキュリティ、拡張性などのカテゴリごとに定量的な基準を示すことが重要です。
機能要件一覧には、各機能の優先度(必須・重要・任意)も併記しておくと、開発フェーズでの判断基準として活用できます。
非機能要件は、定性的な記述(「高い可用性を確保する」など)だけでは基準があいまいになるため、「稼働率99.9%以上」「レスポンスタイム2秒以内」のように数値で定義することが原則です。
システム構成図・業務フロー図
システムの全体構成と業務の流れを図として可視化し、関係者間の共通理解を促進します。
システム構成図では、サーバー、ネットワーク、外部システムとの連携関係を視覚的に示し、業務フロー図では、システム導入後の業務プロセスと各工程でのシステムの関わり方を明確にします。
業務フロー図は、BPMN(Business Process Model and Notation)などの標準的な記法を用いると、関係者間での認識のずれを防ぎやすくなります。また、データの流れを示すデータフロー図(DFD)やデータモデルを示すER図も、システムの全体像を理解するうえで有効な補足資料です。
文章だけでなく図表を併用することで、IT分野に詳しくない発注側の関係者にも理解しやすい要件定義書となります。
スケジュール・体制・前提条件と制約事項
開発の全体スケジュール、プロジェクト体制、そして前提条件と制約事項を記載します。各工程のマイルストーンと期間を明示するとともに、発注側・開発側それぞれの役割分担と責任範囲を定義し、プロジェクトの推進体制を明確にしておくことが不可欠です。
前提条件には、「既存データの移行は発注側が準備する」「テスト環境は開発側が用意する」といった双方の責任範囲に関わる事項を記載し、制約事項には、予算上限、利用可能な技術やインフラの制約、法規制への対応要件などを含めます。
前提条件と制約事項を明文化しておくことで、プロジェクト進行中の認識のずれやトラブルを未然に防ぐことが可能です。
要件定義を成功させるためのポイント
要件定義の品質を高めるためには、プロセスの進め方だけでなく、体制やコミュニケーションの工夫も重要です。ここでは、要件定義を成功に導くための3つの実践的なポイントを解説します。
- 発注側と開発側が密に連携できる体制を構築する
- プロトタイプや画面モックを活用して認識を合わせる
- 上流工程の経験が豊富な開発パートナーを選定する
発注側と開発側が密に連携できる体制を構築する
要件定義の成功には、発注側と開発側の継続的かつ密なコミュニケーションが不可欠です。発注側からは業務に精通したキーパーソンをアサインし、開発側からは業界知識と技術力を兼ね備えたSEやPMを配置することで、双方の視点を融合した精度の高い要件定義が実現できます。
定期的なミーティングの実施はもちろん、課題やQ&Aを管理する共有ツールを活用し、情報の属人化を防ぐ仕組みづくりも重要です。要件定義は一方的に開発側が進めるものではなく、発注側が主体的に参画してこそ品質が担保されます。
発注側の担当者がITに詳しくない場合は、開発側が専門用語を避け、具体的な事例やサンプルを用いて説明する配慮がコミュニケーションの質を高めます。
プロトタイプや画面モックを活用して認識を合わせる
文書だけで要件を共有しようとすると、発注側と開発側の間に完成イメージのずれが生じやすくなります。プロトタイプ(試作品)や画面モックアップ(画面の見本)を早い段階で作成し、発注側に視覚的に確認してもらうことで、認識のずれを開発工程に入る前に解消できます。
画面モックは、実際に動作するシステムである必要はなく、画面レイアウトやボタン配置、データの表示イメージを示すだけでも十分な効果を発揮します。「この画面から受注情報を入力する」「検索結果はこの形式で一覧表示される」といった形で、ユーザーの操作イメージを具体化できるためです。
プロトタイプを用いた確認作業は、手戻りの防止とユーザー満足度の向上の両面で高い効果が期待できます。
上流工程の経験が豊富な開発パートナーを選定する
要件定義の品質は、担当するSEやPMの経験値に大きく依存します。発注側の業界や業務への理解が深く、上流工程の実績が豊富な開発パートナーを選定することが、要件定義を成功させるための最も重要な前提条件です。
上流工程に強い開発パートナーは、発注側の要望の裏にある本質的な課題を見抜く力をもっており、表面的な要望をそのまま要件に落とし込むのではなく、「本当に解決すべき課題は何か」を発注側とともに掘り下げ、最適なシステム像を提案できる点が大きな強みです。
開発パートナーを選定する際は、技術力だけでなく、要件定義や基本設計の実績、業界特有の業務知識の有無、コミュニケーションの質を総合的に評価することを推奨します。
ブライセンなら細かい要件定義で開発の失敗を防ぐ
システム開発プロジェクトの失敗原因として最も多いのが、曖昧な要件定義です。発注側と開発側の認識のズレが、想定外の追加費用や納期遅延、期待外れの成果物を生み出してしまいます。ブライセンでは、こうした失敗を防ぐため、プロジェクト開始前の要件定義フェーズに特に力を入れています。
私たちは100社を超える開発実績から培った独自のヒアリングノウハウを活用し、お客様のビジネス課題を深く理解することから始めます。単に「どんなシステムが欲しいか」ではなく、「なぜそのシステムが必要なのか」「どんな成果を期待しているのか」まで掘り下げて確認。その上で、機能要件・非機能要件を明確に文書化し、認識のズレが生じない仕様書を作成します。
また、開発途中での仕様変更にも柔軟に対応できる体制を整えており、お客様と二人三脚で最適なシステムを構築します。細部まで詰めた要件定義で、開発の失敗リスクを最小限に抑えます。
まとめ
要件定義は、システム開発の最上流工程に位置し、プロジェクト全体の品質・コスト・納期を左右する極めて重要な工程です。機能要件、非機能要件、業務要件、技術要件を漏れなく定義し、要件定義書として文書化したうえで関係者間の合意を得ることが、後続工程をスムーズに進めるための基盤となります。
要件定義を成功させるためには、発注側と開発側の密な連携体制の構築、プロトタイプを活用した早期の認識合わせ、そして上流工程の経験が豊富な開発パートナーの選定が重要なポイントです。
自社のシステム開発を成功に導くために、要件定義の進め方と品質に十分な時間とリソースを投じて取り組んでいきましょう。